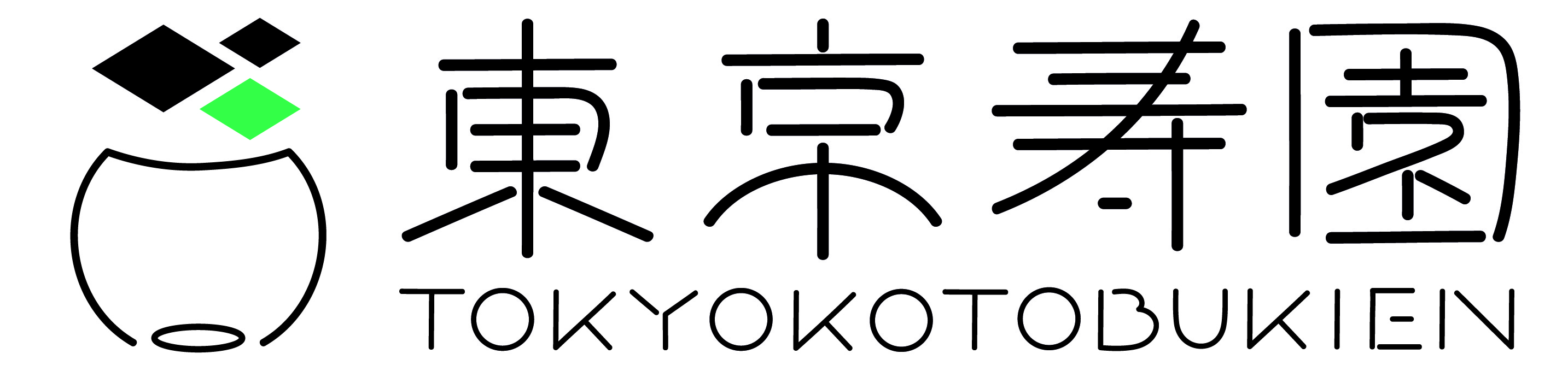目次
皆さんは観葉植物を育てた経験はありますか?観葉植物にはお部屋をきれいに飾ったり、癒しを与えてくれる効果があります。 今回紹介する観葉植物はつる性であるハツユキカズラ。ハツユキカズラは白とピンクの斑模様がキレイな植物で、お部屋のインテリアとしても評判です。 「ハツユキカズラの育て方に自信がない!」「ハツユキカズラを立派に育てる方法が知りたい」という方に向けて以下の内容をまとめました。
 「そもそもハツユキカズラについてよく分からない」という方もいるかと思います。育て方を解説する前ハツユキカズラの基本情報と特徴について解説していきますね。
「そもそもハツユキカズラについてよく分からない」という方もいるかと思います。育て方を解説する前ハツユキカズラの基本情報と特徴について解説していきますね。
 ここからはハツユキカズラの育て方について解説、最初は置き場所から紹介していこうと思います。ハツユキカズラの育て方に悩んでいる方はぜひ見ていってくださいね。
ここからはハツユキカズラの育て方について解説、最初は置き場所から紹介していこうと思います。ハツユキカズラの育て方に悩んでいる方はぜひ見ていってくださいね。
 続いて紹介する育て方は水やりでの育て方について。鉢植えと地植えそれぞれの水やりについて解説していきますね。
続いて紹介する育て方は水やりでの育て方について。鉢植えと地植えそれぞれの水やりについて解説していきますね。
 次に紹介する育て方ポイントは土の選定について。ハツユキカズラに合った用土選びも育て方の重要な要素の1つですので、ぜひ見ていってくださいね。
次に紹介する育て方ポイントは土の選定について。ハツユキカズラに合った用土選びも育て方の重要な要素の1つですので、ぜひ見ていってくださいね。
 最後に紹介する育て方は肥料について。肥料も水と同様に与えるタイミングと分量が重要となってきます。ここでは肥料の与え方について解説していきます。
最後に紹介する育て方は肥料について。肥料も水と同様に与えるタイミングと分量が重要となってきます。ここでは肥料の与え方について解説していきます。

 ハツユキカズラは丈夫な植物ですが、枯れる可能性は0ではありません。ここではハツユキカズラが枯れてしまう原因とその対処法について紹介していきます。
ハツユキカズラは丈夫な植物ですが、枯れる可能性は0ではありません。ここではハツユキカズラが枯れてしまう原因とその対処法について紹介していきます。
 番外編として土ではなく、苔玉での育て方についても解説していきます。苔玉での育て方に興味のある方はぜひ参考に見ていってくださいね。
番外編として土ではなく、苔玉での育て方についても解説していきます。苔玉での育て方に興味のある方はぜひ参考に見ていってくださいね。
- ハツユキカズラの基本情報と特徴
- ハツユキカズラの育て方
- ハツユキカズラのお手入れ方法
- ハツユキカズラが枯れる原因とその対処法
- ハツユキカズラを苔玉で育成する方法
そもそもハツユキカズラってどんな植物なの?

日本や東アジアを原産とするキョウチクトウ科テイカカズラ属の植物
ハツユキカズラはキョウチクトウ科テイカズラ属の多年草で、主な原産地は日本や朝鮮半島など東アジアを中心としています。つる性の植物なのでとても長く育ちますが、まとまって育つため草丈は5~15cmとそこまで大きくなりません。そのためお部屋にコンパクトに飾ることもできますよ。 よく似ている品種にあげられるテイカカズラがありますが、ハツユキカズラはテイカカズラから生まれた園芸品種です。そのため姿かたちがよく似ていますが特徴が少し異なり、ハツユキカズラはテイカカズラに比べて葉や節が小さく成長も遅いです。雪のように白く染まる斑入りの葉が特徴
ハツユキカズラの「ハツユキ」は初雪(はつゆき)が由来となっており、その名の通り白い斑模様が不定形にあってとても綺麗な植物です。他にもピンク色の斑模様も見れますので興味がある方はハツユキ(初雪)カズラの育成を検討してみてくださいね。暑さ、寒さ、日陰に強い丈夫な植物
ハツユキカズラは耐暑性・耐寒性にとても優れており、-5℃~35℃まで耐えることができます。とはいえ最適温度は10℃~25℃程度なので環境調整はしてあげてください。耐陰性もそこそこ備わっており、日当たりの悪い場所でも栽培することができます。ただし、こちらも明るい日陰がベストポジションなので明るい日陰に置けそうであればそちらがオススメです。常緑性だが寒さに当たると紅葉する
ハツユキカズラは常緑性の植物ですが、寒さに当たるとピンクや赤色に紅葉します。しかし上手に育てなければ綺麗な紅葉にならないこともあるようなので、これから紹介する育て方を参考に見ていってくださいね。ハツユキカズラの育て方のポイント①置き場所

風通しの良い半日陰~日向で管理する
ハツユキカズラは耐陰性があり多少暗くても大丈夫ですが、元気に栽培するためには半日陰~日向で管理する育て方がオススメです。ある程度の日光を確保しなければ大きく育てることができません。日光が足りないと葉がきれいに発色しないことも
日光が斑模様が現れないこともあります。白い斑模様には葉緑体がないため、光合成ができません。そのため日光不足を感じると白い斑模様が現れにくくなる可能性がありますので、日光がよく当たる場所を用意しましょう。室内や日陰に置いていた場合は徐々に日光に慣らす
ハツユキカズラを室内や日陰に置いていた場合、急に日光がよく当たる環境に置くとびっくりして大きなストレスとなってしまいます。徐々に日光に慣らしながら環境を変えてあげましょう。夏の直射日光と乾燥に注意
ハツユキカズラは日光の当たる場所を好みますが、真夏の直射日光に長時間あてすぎると葉焼けを起こしてしまいます。暑い季節は涼しい半日陰の場所に置くようにしてください。またハツユキカズラは乾燥にも弱く、乾燥しすぎると落葉してしまいます。水はたっぷりあげ、葉水などで乾燥対策もしましょう。冬の寒風が当たらないようにする
冬の寒風にさらされると葉が枯れてハツユキカズラが死んでしまったと思う方もいますが、ハツユキカズラは毎年花を咲かせる多年草です。春になれば新しい芽がでてくるので、掘り起こさず春を待ってくださいね。ハツユキカズラの育て方のポイント②水やり

地植えの場合:乾燥期以外の水やりは基本的に不要
地植えの場合地中から水が上がってくるので、雨が降らない乾燥機以外の水やりは基本的に必要ありません。毎日水やりしてしまうと水分過多で根腐れを起こしてしまうため注意が必要です。鉢植えの場合
鉢植えの場合は地植えと違う育て方になり、水やりのタイミングと分量に注意しなければなりません。水やりのポイントについて解説していきますね。土が乾き始めたらたっぷりと
水やりのタイミングとしては土が乾いた時です。鉢の底から水が出るまでたっぷりあげるようにしてください。土が乾ききる前に水やりを繰り返してしまうと鉢内が蒸れて、根腐れを起こしてしまうことがあります。根腐れを起こすと枯れてしまうので注意しましょう。夏は涼しい時間帯に2回行う
暑い真夏の時期は朝・夕の涼しい時間帯に1回ずつ水やりをしましょう。夏の暑い時期は乾燥しやすいため、2回水やりをして乾燥を防ぎましょう。冬は水やりを控えめに
休眠期の冬は水をそこまで必要としません。土も乾燥しにくくなるため、水やりは土が乾いた2~3日後に少量の水を上げるようにしてください。ハツユキカズラの育て方のポイント③土

水はけがよく通気性のある土を好む
ハツユキカズラは水をたっぷりあげて育てます。そのため水はけの悪い土を選んでしまうと鉢内に湿気が溜まりやすくなって根腐れをおこしてしまいます。最後には枯れてしまうことになるので、水はけのいい土を選ぶようにしてください。地植えの場合:腐葉土や完熟堆肥など有機質資材を混ぜ込む
地植えで育てる場合は腐葉土や完熟堆肥など有機質のものを混ぜ込みましょう。土の通気性・透水性の向上や肥料成分・保肥力にも優れるためハツユキカズラに相性ピッタリの土壌になります。鉢植えの場合
鉢植えでの育て方は地植えとは条件が大きく異なるため、用意する土が変わってきます。鉢植えでの土選びについて解説していきますね。市販の花用培養土で育てられる
ハツユキカズラを鉢植えで育てる場合、ホームセンターや園芸店にある市販の花用培養土で十分育てることができます。土の配合に困ったら水はけの良い花用培養土を選ぶのもいいですよ。赤玉土7:腐葉土3の配合土
赤玉土・腐葉土はどちらも保水性・排水性・保肥性に優れており、水を多く上げて育てるハツユキカズラとは相性がピッタリです。赤玉土7:腐葉土3の組み合わせがちょうどいいのでおすすめですよ。赤玉土6:腐葉土3:バーミキュライト1の配合土
赤玉土6:腐葉土3:バーミキュライト1の組み合わせもおすすめです。バーミキュライトは穴の開いた構造であるため、通気性・排水性・保肥性・断熱性・保温性に優れています。バーミキュライトを少し加えることでさらに良い土になるのでこちらもおすすめです。ハツユキカズラの育て方のポイント④肥料

元肥:緩効性化成肥料を植え付け時に用土に混ぜる
植え替えや植え付けのタイミングに元肥として用土に混ぜ込む与え方があります。この方法であれば、植え付け時ついでに行えるので効率よく肥料を与えることができます。追肥
ハツユキカズラの生育に合わせて追肥を与える場合の要点・注意点がいくつかあるので紹介していきます。4月~10月の生育期に行う
ハツユキカズラの生育期は4~10月。肥料を与えるのは生育期のみで大丈夫です。それ以外の休眠期に肥料を与えてしまうと栄養過多で「肥料焼け」を起こして枯れてしまう恐れがありますので注意してください。緩効性肥料を置き肥
固形肥料である緩効性肥料を使う場合は2か月に1回程度のペースで置き肥して使ってください。使用時はその製品に定められた分量を守って使うようにしましょう。液肥を定期的に与える
液体肥料は即効性が高いので、与えてすぐに効果が得られます。その分効果が切れるのも早いので、2週間に1回ペースで与えるようにしましょう。 液体肥料は即効性が高く効果が強い分、特に与えすぎに注意しなければなりません。基本的に水に薄めて使うものなので扱いには注意してくださいね。肥料分が足りないと葉の発色が悪くなることも
ハツユキカズラの肥料分が不足していると葉の発色が悪くなることがあります。きれいな赤やピンク色が見たい方は生育期に肥料を与えながら育てるようにしてください。ハツユキカズラのお手入れ

ハツユキカズラはある程度成長するとお手入れが必要となってきます。お手入れや管理が甘いと元気な姿にならなかったりするので、不安な方はぜひ参考に見ていってくださいね。
植え付け・植え替え
ここでは植え付け・植え替えについて解説していきます。この作業を怠ると根詰まり・根腐れを起こして、枯れる原因となってしまうので気を付けてください。時期:4月上旬~7月上旬、9月中旬~10月下旬
植物の植え付け・植え替えはストレスを与えてしまう作業です。そのためその植物の元気な時期に行うことが大切。ハツユキカズラの場合は4月上旬~7月上旬、9月中旬~10月下旬がおすすめです。真夏の8月は暑すぎて回復が難しい場合があるので避けたほうがいいでしょう。植え付けのしかた
植え付けの方法は以下の通り。- 土作りをした場所に根鉢より一回り大きな穴を掘る
- 軽く根鉢をほぐす
- 穴にハツユキカズラを植え込んだら水をたっぷりあげて完了。
植え替えのしかた
植え替えの方法は以下の通り。- 株より一回り大きな鉢を用意する
- 用意した鉢に鉢底ネットを敷く
- 鉢底ネットが見えなくなるまで鉢底石(軽石)を敷く
- 鉢の1/3程度まで土を入れておく
- 古い鉢からハツユキカズラを取り出して根鉢をほぐす
- 黒く傷んだ根っこを全て剪定して新しい鉢に置く
- 鉢縁から3cm程度下まで土を入れる
- 鉢底から水が流れ出るまで水を与えて完了
剪定
ハツユキカズラが大きくなると選定作業も必要になってきます。整った元気なハツユキカズラにするには選定は欠かせないので参考に見ていってくださいね。切り戻しを行うことで新芽が出る
伸びすぎた枝を切り戻し選定することで見た目がスッキリし、切り戻した部分から新芽が出てくるので見た目のリフレッシュもすることができます。また新芽は発色が良いため、きれいなハツユキカズラになりやすくなります。花を楽しみたい場合は花後に剪定する
ハツユキカズラは多年草であるため毎年きれいな花を咲かせます。5~6月ごろに花を咲かせるので、花を楽しみたい方はそのあとに選定作業を行いましょう。先祖返りした枝は切り取る
ハツユキカズラの白い斑模様は先祖返りして緑色の葉っぱに戻ってしまうことがあります。先祖返りした葉っぱを残しておくと、その周りの白斑にも影響して緑色になってしまいますので先祖返りした葉っぱはなるべく選定するようにしてください。増やし方
ハツユキカズラは成長すれば増やすこともできるようになります。ここではハツユキカズラの増やし方をいくつか紹介していきます。挿し木
挿し木とは成長したハツユキカズラの枝を選定して増やす方法です。挿し木の方法は元気な枝を選んで、別の鉢に挿して発根させることで新たにハツユキカズラを増やしていきます。挿し木は簡単な方法なので初心者にもおすすめですよ。取り木
取り木とは幹や枝の一部の表皮を切り取ってそこから発根させて増やす方法です。発根させることができたら、そこから切り取って別の鉢に入れて新たに育てていきます。この方法は少し難しいので園芸に慣れた方にオススメの方法です。ハツユキカズラが枯れる原因と対処法

枯れる原因
ハツユキカズラが枯れる原因は以下の通り。乾燥
ハツユキカズラは乾燥に弱い植物です。水不足にならないように管理したり、エアコンの風が当たってしまう場所に置かないように注意してください。根腐れ
風通しの悪い場所に置いてしまったり、水の与えすぎによって鉢内が蒸れてしまい根腐れを起こしてしまうことがあります。根腐れを起こすと枯れてしまう危険性が大きくなってしまうので、ならないように管理してあげることが重要です。直射日光による葉焼け
ハツユキカズラは長時間、直射日光にさらされ続けると葉焼けを起こしてしまいます。葉焼けを起こした部分は光合成ができなくなってしまうため、最終的に元気がなくなり枯れる要因となってしまいます。 カーテンレース越しや、遮光ネット越しの日光に当たる場所においてあげましょう。根詰まり
根詰まりはハツユキカズラが成長して鉢内が根っこで満たされて栄養の吸収を互いに阻害しあってしまう現象です。根詰まりを防止するには定期的な植え替えが必要になります。目安としてですが、2~3年に1回は植え替えを行うようにしてください。冬の寒風に当たった
ハツユキカズラは寒さに高く-5℃まで耐えることができますが、冬の寒風には耐えることが難しいです。自身の育てている環境を確認して耐えられるかどうか確認しましょう。厳しそうであれば冬は室内で冬越しさせるようにしてください。肥料不足
単純に肥料が足りていない可能性があります。生育期に合わせて肥料を与えてください。ただし肥料を与えすぎると肥料焼けを起こして枯れてしまいます。肥料の与えすぎにも注意しましょう。対処法
ハツユキカズラが枯れないようにする対処法を紹介していきます。ここで解説することに注意すればハツユキカズラを元気に育てることができるので参考にしてくださいね。剪定を行う
悪くなった葉っぱの選定を行うことで、新芽が出て葉の色づきも良くなります。密集した葉っぱをスッキリさせて全体の日当たりも良くなるので剪定はハツユキカズラの健康状態にとても良い作業ですよ。植え替えを行う
土が古くなったり根詰まりを起こすとハツユキカズラの成長が悪くなります。定期的に植え替えを行い新たな土に変えてあげることで元気な成長を促すことができますよ。肥料を与える
生育期の期間は肥料を与えることをおすすめします。肥料を与えることで発色がよくなり、ハツユキカズラの健康にもいいですよ。 ただし生育期以外の期間は肥料を必要としません。そんな状態で肥料を与えてしまうと簡単に肥料焼けを起こしてしまうので注意してくださいね。【番外編】苔玉での育て方

ハツユキカズラは苔玉で売られていることも
ハツユキカズラは鉢植えではなく、苔玉に植えられた状態で販売されていることもあります。自分で用意するのが面倒だと思った方は苔玉に植えられているのを購入するのもいいかと思います。苔玉での管理のしかた
苔玉での管理方法について解説していきます。苔玉で育てたいと考えている方は参考に見ていってくださいね。よく日の当たる風通しの良い場所で育てる
苔玉にはよく水を吸わせて育てます。日当たりが悪く風通しの悪いジメジメした場所で育てると根腐れを起こしてしまう恐れがあり、さらに光合成ができません。生育に良くないので日当たりが良く、風通しのいい場所に置いてあげましょう。蒸れに弱いため室内に置くのは難しい
ハツユキカズラは湿気に弱いため、室内での管理が難しいです。基本的には明るい日陰の玄関などがちょうど良くオススメです。2日~3日に1回を目安に、苔玉を水につける
苔玉は保水性が高いため、毎日水につける必要はありません。毎日水につけてしまうと根腐れを起こしやすくなってしまいます。2~3日に1回程度苔玉を水につけてください。苔玉は自作することも!
中には苔玉を自作してきれいに飾る人たちも存在します。苔玉自作について紹介していきますね。「趣味の園芸」で方法が紹介されている
NHK出版の「趣味の園芸」でも苔玉の自作方法が紹介されています。苔玉作りに興味がある方はぜひ趣味の園芸も参考にしてみてくださいね。泥団子をつくり、コケを巻く
苔玉用の用土としてケト土、赤玉土小粒、水苔をよく混ぜ合わせて泥団子状にします。泥団子にハツユキカズラを挿して苔玉を巻いたら完了です。そのまま定期的に水に浸しながら育ててください。【まとめ】ハツユキカズラの育て方を徹底解説!お手入れ方法から苔玉での育て方まで
ここまでハツユキカズラの育て方や特徴について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?ハツユキカズラは白斑が特徴的で秋も紅葉するので、とても楽しみが多い観葉植物だということが分かっていただけたかと思います。ここまでの内容をまとめると以下の通り。- ハツユキカズラは耐寒性・耐暑性が高く-5℃~35℃まで耐えることができる
- ハツユキカズラの草丈は5~15cm程度でお部屋に飾りやすい
- ハツユキカズラは水はけの良い土を好む
- ハツユキカズラの生育期は4~10月
- ハツユキカズラは挿し木、取り木で増やせる