モウセンゴケの育て方を紹介!特徴からトラブルの正しい対処法まで
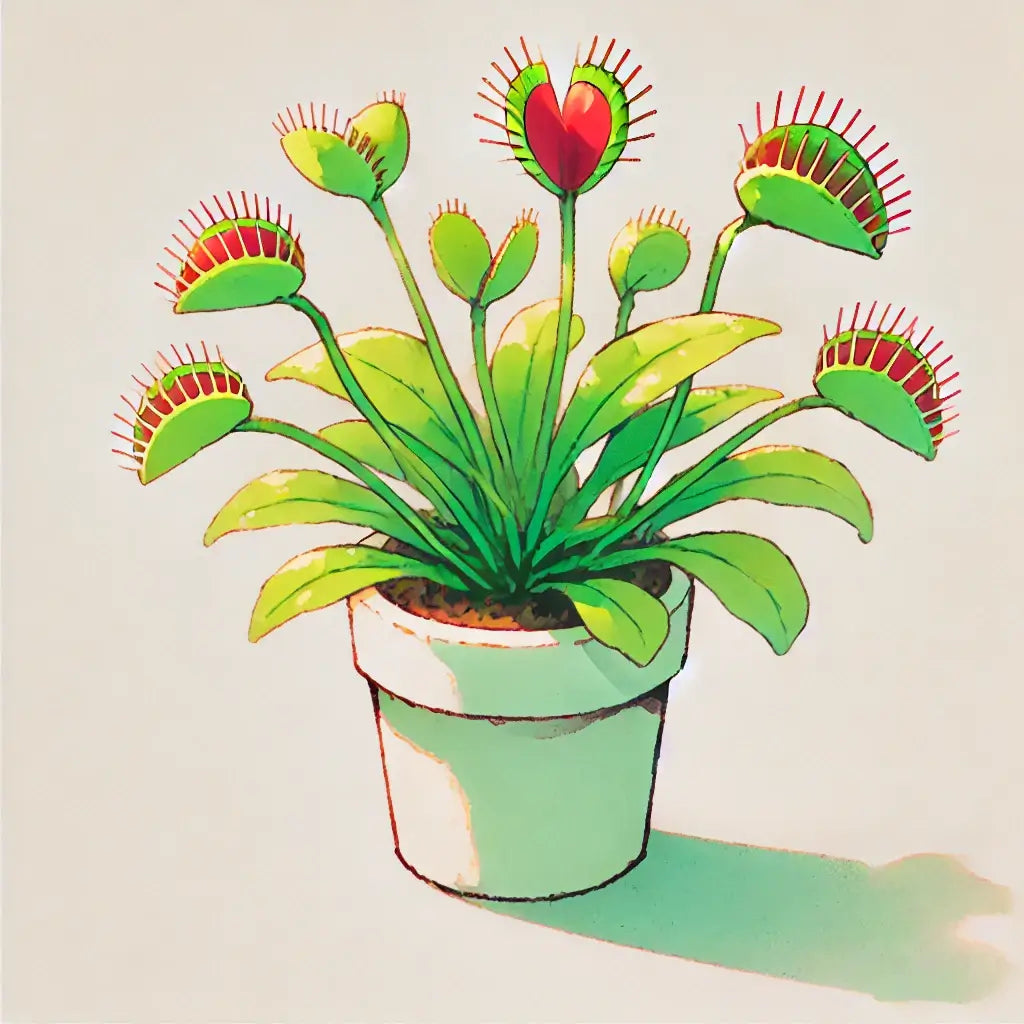
皆様はモウセンゴケ(ドロセラ)と言う植物をご存じですか?モウセンゴケは食虫植物として知られており、粘液を出して虫を食べる人気の植物です。まだ見たことのない方も多い植物かもしれませんが、実際には赤い葉を持つ綺麗な植物でもあり、自宅でも育てることができます。 今回の記事では「モウセンゴケ(ドロセラ)の育て方」をテーマに、どんな植物なのかや、基本的な育て方、増やし方まで以下の流れで解説していきます。
 それではまずはモウセンゴケがどんな植物なのかについて、基本情報からその特徴、不思議な花言葉まで解説していきます。モウセンゴケはかなり奥が深い植物なので、ぜひ楽しみながら学んでいきましょう。
それではまずはモウセンゴケがどんな植物なのかについて、基本情報からその特徴、不思議な花言葉まで解説していきます。モウセンゴケはかなり奥が深い植物なので、ぜひ楽しみながら学んでいきましょう。
 続いてはモウセンゴケの植え付けについて解説していきます。ここまででお分かりいただけたように、モウセンゴケは一般的な植物や花とは違い、食虫植物という珍しい品種の植物のため、必要な知識やコツが他のものと変わってきます。その点もしっかりと参考にしてみてください。
続いてはモウセンゴケの植え付けについて解説していきます。ここまででお分かりいただけたように、モウセンゴケは一般的な植物や花とは違い、食虫植物という珍しい品種の植物のため、必要な知識やコツが他のものと変わってきます。その点もしっかりと参考にしてみてください。
 続いてはこの記事の本題でもある、モウセンゴケの育て方について解説していきます。ここからは特に肝心な4つのポイントを解説していきます。まずは栽培場所についてお話ししていきます。
続いてはこの記事の本題でもある、モウセンゴケの育て方について解説していきます。ここからは特に肝心な4つのポイントを解説していきます。まずは栽培場所についてお話ししていきます。
 続いてのモウセンゴケの育て方のポイントは水やりです。水やりはモウセンゴケの育て方のポイントにおいて、他の植物とは違うものもありますよ。それではモウセンゴケの水やりを見ていきましょう。
続いてのモウセンゴケの育て方のポイントは水やりです。水やりはモウセンゴケの育て方のポイントにおいて、他の植物とは違うものもありますよ。それではモウセンゴケの水やりを見ていきましょう。
 続いてのモウセンゴケの育て方のポイントは土です。モウセンゴケは他の植物とは違った特徴や育て方をしないといけないので、土もこだわってあげる必要があります。それではどんな土がいいのかお話ししていきます。
続いてのモウセンゴケの育て方のポイントは土です。モウセンゴケは他の植物とは違った特徴や育て方をしないといけないので、土もこだわってあげる必要があります。それではどんな土がいいのかお話ししていきます。
 最後のモウセンゴケの育て方のポイントは、肥料になります。肥料は先ほどの土のポイントでもお話ししたようにそこまで重要な要素ではありません。だからこそ、いつどれくらい肥料が必要かをお話ししていきます。
最後のモウセンゴケの育て方のポイントは、肥料になります。肥料は先ほどの土のポイントでもお話ししたようにそこまで重要な要素ではありません。だからこそ、いつどれくらい肥料が必要かをお話ししていきます。
 続いてはモウセンゴケが成長した時にすることの、植え替えについて解説していきます。「モウセンゴケの植え替えは大変そう...」とイメージで思われている方も多いかもしれませんが、実はそこまで難しくないですよ。一つずつ手順や時期を見ていきましょう。
続いてはモウセンゴケが成長した時にすることの、植え替えについて解説していきます。「モウセンゴケの植え替えは大変そう...」とイメージで思われている方も多いかもしれませんが、実はそこまで難しくないですよ。一つずつ手順や時期を見ていきましょう。
 続いてはモウセンゴケの増やし方について解説していきます。モウセンゴケの増やし方を、ここでは合計4種類ご紹介して行きます。初心者の方にも分かりやすく解説しているのでぜひお好きな増やし方に挑戦してみてください。
続いてはモウセンゴケの増やし方について解説していきます。モウセンゴケの増やし方を、ここでは合計4種類ご紹介して行きます。初心者の方にも分かりやすく解説しているのでぜひお好きな増やし方に挑戦してみてください。
 続いてはモウセンゴケに起こりやすいトラブルについて解説して行きます。モウセンゴケに起こりやすトラブルとは一体なんなのか、またどのようにトラブルに対処するといいのかについて解説して行きます。
続いてはモウセンゴケに起こりやすいトラブルについて解説して行きます。モウセンゴケに起こりやすトラブルとは一体なんなのか、またどのようにトラブルに対処するといいのかについて解説して行きます。
 最後はモウセンゴケの種類をご紹介して終わりにしようと思います。モウセンゴケはかなり多くの種類が確認されている植物のため、選ぶのもまた一つの楽しみでしょう。4つご紹介するのでぜひお好きなものを選んでみてはいかがでしょうか?
最後はモウセンゴケの種類をご紹介して終わりにしようと思います。モウセンゴケはかなり多くの種類が確認されている植物のため、選ぶのもまた一つの楽しみでしょう。4つご紹介するのでぜひお好きなものを選んでみてはいかがでしょうか?
- モウセンゴケはどんな植物?基本的な特徴を解説
- モウセンゴケの植え付けのコツ
- モウセンゴケの育て方のポイント①〜④栽培場所・水やり・土・肥料
- モウセンゴケが成長したらするべき植え替えについて
- モウセンゴケの増やし方を解説
- モウセンゴケに起こりやすいトラブルって何?
- モウセンゴケの種類を4つご紹介!
- まとめ
モウセンゴケってどんな植物なの?

モウセンゴケ科モウセンゴケ属の食虫植物
モウセンゴケはモウセンゴケ科モウセンゴケ属の食虫植物です。食虫植物はその名の通り、虫を食べる植物で、虫を捕食しながら生きる珍しい植物です。モウセンゴケと言うだけあってコケの仲間なのかと誤解する方もいますが、モウセンゴケは花を咲かせるのでコケの仲間ではありません。腺毛から出た粘液で虫をとらえる
モウセンゴケは腺毛と呼ばれる葉の表面の先から粘液を出し、引っ付いた虫を捕らえる食虫植物です。緑色の葉っぱと本体のピンク色のカラーのコントラストは、食虫植物好きの方には非常に人気があります。花言葉
続いてはモウセンゴケの花言葉について解説していきます。モウセンゴケは食虫植物というだけあって、少し珍しい花言葉を持っていますよ。それでは6つの花言葉があるので見ていきましょう。あなたに捧げる恋の歌
1つ目は「あなたに捧げる恋の歌」です。「あなたに捧げる恋の歌」という花言葉は、特徴の甘い香りを出して虫を誘き寄せるモウセンゴケの習性が由来しているともいわれています。セレナーデ
2つ目は「セレナーデ」です。「セレナーデ」という言葉自体どういう意味なのかというと、夕べや夜に恋人の窓下で歌い奏でられる音楽という意味です。モウセンゴケの実は儚いその食虫植物という特徴が、このような花言葉に由来するのでしょう。詐欺
3つ目は「詐欺」です。「詐欺」という花言葉は、まさにモウセンゴケの食虫植物の特徴が反映されている花言葉です。騙して虫を誘き寄せる姿が、そのように見えたのでしょう。不誠実
4つ目は「不誠実」です。「不誠実」という花言葉は、先ほどの「詐欺」という花言葉と似た由来を持っています。誠実ではなく不誠実という花言葉なので、基本的には贈る相手を選ばなくてはいけません。無神経
5つ目は「無神経」です。「無神経」という花言葉は、まさにモウセンゴケに捕食される虫たちを見て、少々残酷に見えたのでしょう。無神経に虫を食す姿に見えたのが、よく想像できます。物思い
6つ目は「物思い」です。「物思い」という花言葉はどちらかというと「詐欺」「不誠実」「無神経」というネガティブな意味の花言葉とは違い、「あなたに捧げる恋の歌」や「セレナーデ」のような、モウセンゴケの習性や特徴を見て花言葉を名付けた方が感じた、切なさに近い花言葉でしょう。モウセンゴケの植え付け

苗の選び方のコツ
まずは、モウセンゴケの苗の選び方のコツについて解説していきます。モウセンゴケの苗の選び方のコツは、以下の3つになります。それでは一つずつ確認していきましょう!葉が多く株元がしっかりしていて太いものを選ぶ
1つ目は、葉が多く株元がしっかりしていて太いものを選ぶことです。葉が多く株元がしっかりしていて太いものを選ぶことで、今後の成長に大きく関わってきます。元気なモウセンゴケを育てるには、まず初めにこうした選択をしましょう。害虫がついていないかよく確認する
2つ目は、害虫がついていないかよく確認することです。害虫がついている苗は、元から害虫の影響で成長が悪く、元に戻っても枯れてしまうことなども考えられるため、害虫がついていないかよく確認しましょう。花は咲いていても咲いていなくてもよい
3つ目は、花は咲いていても咲いていなくてもよいことです。元からモウセンゴケは丈夫な植物でもあります。そのため、花が咲いていても咲いていなくても、後々元気に育てていけば花は咲くので、苗の状態では気にしなくOKです。植え付けのしかた
続いてはモウセンゴケの植え付けのしかたについて解説していきます。一つずつステップを踏めばそこまで難しくないのですが、他の植物とは違う植え付け方になるので初めはゆっくりと丁寧に行いましょう。鉢に土を入れる
まず鉢に土を入れましょう。この時鉢は、深めの鉢などではなく浅めの鉢を使うことで栽培しやすくなります。盆栽鉢などを使うのもおすすめです。また湿度の高い土を好むので、しっかりと湿らせた土を鉢に入れましょう。苗を鉢の中心に置き、隙間に水苔を詰める
続いては、苗を鉢の中心に置き、隙間に水苔を詰めましょう。湿度を保ち乾燥を防ぐために水苔を優しく巻くように隙間を埋めながら詰めていきます。深く植えないように注意する
最後は深く植えないように注意します。元から浅い鉢にしているのでそこまで深く植えることはできませんが、それでも浅めに植えるように心がけましょう。ここまで、難しいようで意外と簡単だったのではないでしょうか?モウセンゴケの育て方のポイント①:栽培場所

風通しの良い明るい場所が適している
モウセンゴケに適した栽培場所は、風通しの良い明るい場所で管理することです。風通しがいいとしっかりとした通気性を確保できます。また、日光が適切に当たることでしっかりとした太いモウセンゴケに育ちます。直射日光の当てすぎによる葉焼けに注意
また、直射日光の当てすぎによる葉焼けに注意しましょう。直射日光はどの観葉植物や花でもそうですが、基本的に当てすぎると葉焼けを起こしてしまいますので、直射日光が当たる場所は避けて管理しましょう。冬は寒風や凍結、霜を避けたベランダなどに置く
最後は、冬は寒風や凍結、霜を避けたベランダなどに置くことです。耐寒性のある種もありますが、基本的には普通〜やや強い程度と覚えておきましょう。そのため、冬は寒風や凍結、霜を避け、葉を凍らせないように注意しましょう。モウセンゴケの育て方のポイント②:水やり

鉢の下に水をためた受け皿を置く
モウセンゴケの水やりの最も大きな特徴は、鉢の下に水をためた受け皿を置く「腰水」という水やり方法をすることです。腰水はまさに受け皿に水を入れたままにして栽培する水やりの方法で、モウセンゴケは湿地に自生する植物なので、水分のある環境が必要な植物です。自生地に近い環境で育てるのがベストです。冬の休眠期も水を切らさないようにする
モウセンゴケは他の植物とは違い、冬の休眠期も水を切らさないようにすることがポイントです。他の観葉植物や多肉植物などは基本的に冬は断水気味にしてあげるのですが、モウセンゴケは冬の休眠期も水を切らさないようにしてあげなければならない品種です。モウセンゴケの育て方のポイント③:土

花用の培養土などは栽培に向かない
モウセンゴケは、結論からお伝えすると花用の培養土などは栽培に向きません。そのため、オリジナルの用土を作るのが最もおすすめなのですが、初心者の方には少し難しいかもしれないのでここからは簡単に説明していきます。保水性・通気性が良く肥料分がないものがよい
モウセンゴケに適している用土は、保水性・通気性が良く肥料分がないものがよいです。保水性・通気性が良いことでちょうどよく水を溜め、乾燥してくれる環境を作れます。しかし元からモウセンゴケは痩せた土地に育つので、肥料は要らず、光合成と水分だけで問題ありません。日向土にピートモスやヤシがらを配合したものもよい
また、特にモウセンゴケにおすすめの土は、日向土にピートモスやヤシがらを配合したものもよいとされています。日向土にピートモスやヤシがらを配合すると土壌の酸度が高まるので、酸性の土壌を好むモウセンゴケにはピッタリです。植え付け部分は水苔が扱いやすくておすすめ
特に、モウセンゴケは何度もお話ししているように湿った環境で自生している植物のため、必ず植え付け部分には水苔を詰めるのが、最も扱いやすくておすすめです。特性に合わせて土を変えることが重要であるというお話しです。モウセンゴケの育て方のポイント④:肥料

肥料は基本的に必要ない
モウセンゴケの肥料は、結論からお伝えすると基本的に必要ありません。先ほどもお話ししたように、元から痩せた土地に自生する植物のため、肥料は必要ありません。きちんと風通しのよい日の当たる場所で育てるだけで、きちんと光合成を利用して元気に育ちます。肥料を与えて栄養が足りると葉が小さくなることも
また、この「肥料を与えなくても育つ」ということを知らないで肥料を与えてしまうと、モウセンゴケは栄養分は増えすぎて逆に肥料焼けを起こし、葉が小さくなってしまうこともあります。虫を与えてあげる必要もない
それに加えて、モウセンゴケは虫を与える必要もありません。しっかりと光合成で栄養を吸収できているので、虫は栄養がどうしてもいない時に食べるサプリのようなものだと考えると楽に育てることができるでしょう。【成長したらすること】モウセンゴケの植え替え

植え替えのタイミング:1~2年に1回が目安
モウセンゴケの植え替えのタイミングは、1~2年に1回が目安と言われています。ここはどんな植物とも同じで、基本的には大きく成長したタイミングで鉢を変えて植え替えする必要があります。植え替えの時期:冬の休眠期
またモウセンゴケの植え替えの時期は、冬の休眠期になります。「暑い時期に植え替えするのが一般的でしょ」と思っていた方は、ここでは新しく、モウセンゴケは冬に植え替えをすると覚えておきましょう。植え替えのしかた
それでは植え替えの手順を見ていきましょう。- モウセンゴケを購入して1~2年が経ち、大きくなっていることが実感できたら植え替えましょう。
- 新しい鉢に日向土を1/4ほどいれ、苗を中央に置き、周りを水苔で詰めていきましょう。
- 隙間が空かないようにしっかりと詰めてください。
- 苗はなるべく浅い場所に植え、深く埋めないようにします。深植えすると根がしっかりと伸びず成長が悪くなってしまいます。
- 最後にたっぷりと水を与えて完成です。
モウセンゴケの増やし方

葉挿し
1つ目は葉挿しです。葉挿しは、土にモウセンゴケを挿して増やす方法です。どのように増やしていくのか、またどのような葉を選んで葉挿しするのがいいのかを、解説して行きます。元気で傷んでいない葉を用いる
まず、モウセンゴケの中でも葉挿しにできそうな元気で傷んでいない葉を選んで増やしましょう。傷んでいる葉はそもそもの生命力が弱い部分もあるため、葉挿しにしようするものは元気なものを選んでください。葉挿しのしかた
- 元気で傷んでいない葉を選び、先から10cmほどに切ります。
- よく湿った水苔の上に、粘液の面を上にして置きましょう。
- 明るめの日陰でそのままにし、発芽するのを待ち、発芽したら鉢に植え替えて完成です。
種まき
2つ目は種まきです。先ほどの葉挿しでは、実は非常に細かい種もできます。この種を蒔いても良いです、ネットショップなどで種から購入してもOKです。それでは種まきによる増やし方をみて行きましょう。夏から秋にかけて種子がとれる
モウセンゴケは夏から秋にかけて種子がよくとれます。そのため、この夏から秋にかけての暑い時期に種をしっかりと収穫することができれば、種をまいてモウセンゴケを増やせるというわけです。保管せずにすぐにまく
また、モウセンゴケの種は、保管せずにそのまますぐに撒くことがおすすめです。すぐに水苔をまいて腰水をし、湿った環境で育てることで発芽することができます。発芽は翌春で、移植は粘液が出てきたころに行う
モウセンゴケの発芽は翌春で、移植は粘液が出てきたころに行いましょう。冬の寒い時期を乗り越えさせることで、しっかりと翌春に発芽することができるモウセンゴケに育てることができます。種まきのしかた
- 夏から秋にかけてとれたモウセンゴケの種子を用意します。
- よく湿った水苔をまいた土に種を蒔きます。この時土は被せないように。
- 腰水をし、常に湿った環境で育てるようにしましょう。
- 夏から秋にかけてまいた種は翌春に発芽します。それまでは常に乾燥しないようにして栽培しましょう。
株分け
3つ目は株分けです。株分けは他の植物でもする増やし方で、かなり王道の増やし方とも言えるでしょう。ここではモウセンゴケの株分けはどの時期に行うのがいいのかについて解説して行きます。3月~5月が適期
モウセンゴケの株分けは、3月~5月が適期と言われています。暑さが出過ぎないこの時期に株分けを行うのが最も株に影響を与えないので推奨しています。株分けのしかた
- 鉢からモウセンゴケを優しく引き抜きます。
- 株を均等に分けて、葉などに偏りがないように2〜3株に分けしましょう。
- 株を分けたら植え付け時と同じように植え付けて完成です。
ムカゴ(球根)での増やし方
4つ目はムカゴです。ムカゴという名前は聞き馴染みのない言葉ですが、イメージは球根のようなものです。球根から増やすこともできるので、そのやり方をここではご紹介して行きます。品種によっては葉の付け根にムカゴ(球根)ができることがある
モウセンゴケの中には、品種によっては葉の付け根にムカゴ(球根)ができることがあります。特にピグミー種と呼ばれるモウセンゴケは、このムカゴ(球根)ができやすいと言われています。ムカゴの植えかた
- 用土を用意します。栄養分の入っていない保水性・通気性が良い土がおすすめです。
- 表面に湿ったピートモスを貼り付け、ムカゴが発芽しやすように土は湿らせておきます。
- そこにピンセットなどでムカゴを乗せましょう。
- 腰水をし、常に湿った環境を作って完成です。
モウセンゴケに起こりやすいトラブル

病気にはほとんどかからない
モウセンゴケは結論からお伝えすると、実は病気にはほとんどかからない丈夫な植物です。しかし、以下のような虫がつくことはあるので、害虫対策のみしっかりと行うようにしましょう。害虫
病気にはほとんどかからないモウセンゴケですが、害虫には注意する必要があります。ここからは、どんな害虫がいて、どのような対処をするのがいいのかについて詳しくお話しして行きます。スリップス
スリップスはよくモウセンゴケについていることで知られています。スリップスは苗で購入したモウセンゴケに初めからついていた可能性も考えられます。そのため、苗で購入するときは、必ず虫がついていないか確認する必要があります。ハダニ
続いてはハダニです。ハダニは植物の葉から栄養を吸収して弱らせます。モウセンゴケにはまれにつくこともありますが、基本的には風通しの良い日の当たる環境で育てていれば虫はつきません。カイガラムシ
カイガラムシは白くもふもふとした毛を持つ昆虫です。白っぽいものが小さくたくさんついている時などは、このカイガラムシを疑いましょう。ハダニ同様に栄養を吸うので注意が必要です。対処法:早めに薬剤を散布する
そんな害虫を対処するのは、早めに薬剤を散布するのが最も効果的です。特に虫が苦手な方や、絶対に害虫を発生させたくない方は特に、早め早めの行動が肝心になってくるので、苗を購入する時に合わせて薬剤も購入するのがおすすめです。暑さ・寒さに気を付ける
また、モウセンゴケは害虫のみならず暑さ・寒さにも気を付けるようにしましょう。どのように気をつけるべきかを解説していきます。冬は凍えないよう日当りが良く夜冷えすぎないベランダなどに置く
まず、冬は凍えないよう日当りが良く夜冷えすぎないベランダなどに置きましょう。耐寒性がそれなりにあるので、寒さで凍らないようにすれば、基本ベランダなどで栽培してOkです。夏は風通しのよく熱のたまらない場所に置き、直射日光を避ける
また、夏は風通しのよく熱のたまらない場所に置き、直射日光を避けながら管理しましょう。直射日光は葉焼けを起こしてしまうので、特に置き場所には注意を払って管理しましょう。粘液が出ない
また、モウセンゴケにとってかなり重要な粘液が出ないというトラブルに関して、なぜそのようなことが起きてしまうのか、またどんな対処をするといいのかについて解説していきます。モウセンゴケは健康な状態のときに粘液を出す
モウセンゴケは本来、健康な状態の時に粘液が出す植物です。そのため、粘液が出ないということは、何かしら健康ではない状態に陥ってしまっていることが考えられます。環境が適しているか見直す
そのため、まずはモウセンゴケに今育てている環境が適しているのかどうかを見直すようにしましょう。水やりや置き場所、肥料を与えてしまっているなどのさまざまな要因の中から今の問題をピックアップして、モウセンゴケにあった環境をまた作り直してあげる必要があります。アフリカナガバモウセンゴケは時期によって粘液が出ない場合がある
しかしながら、モウセンゴケの中の種類のアフリカナガバモウセンゴケは時期によって粘液が出ない場合がありますので、ぜひここは単純に記憶して覚えていただくのがいいでしょう!モウセンゴケの種類

アデラエ:大型で10㎝~20㎝ほどの葉をつける
1つ目はアデラエです。アデラエは大型で10㎝~20㎝ほどの葉をつけるのが特徴的なモウセンゴケです。ネットショップなどでも簡単に購入できるため、家にいながら好きなアデラエを購入することができおすすめです。カペンシス:モウセンゴケの中で最も古くから栽培された品種
2つ目はカペンシスです。カペンシスはモウセンゴケの中で最も古くから栽培された品種として知られている人気のモウセンゴケです。長さ4~6cmの細長いへら状の葉の先端には多数の赤い腺毛があり、底から粘液を分泌して虫を捕まえます。ハミルトニー:小型のロゼット種で、日本に多く出回るようになった種
3つ目はハミルトニーです。ハミルトニーは小型のロゼット種で、日本に多く出回るようになった種です。オーストラリア南西部に自生するモウセンゴケで、小さく肉厚な葉っぱがキュートな植物なので、小さいモウセンゴケが欲しい方にはおすすめです。ビナータ:大型で葉が30㎝以上になることも
4つ目はビナータです。ビナータは大型で葉が30㎝以上になることもあるモウセンゴケです。何と言っても大きな葉っぱが特徴的で、かなりのボリューム感のあるモウセンゴケを探している方にはおすすめの品種になります。モウセンゴケの育て方を紹介!特徴からトラブルの正しい対処法までのまとめ
いかがだったでしょうか?モウセンゴケがどんな特徴を持った植物であるか、またどのように育てるとより元気に育つのかがしっかりとご理解いただけたかと思います。 この記事のポイントは以下になります。- モウセンゴケはモウセンゴケ科モウセンゴケ属の食虫植物
- モウセンゴケの花言葉は「あなたに捧げる恋の歌」「不誠実」「無神経」「詐欺」などがある
- 苗は害虫がついていないかしっかりとみて選ぶ
- モウセンゴケは風通しのいい明るい場所で管理するのがおすすめ
- 鉢の下に水をためた受け皿を置く「腰水」という水やり方法をする
- モウセンゴケに適している用土は、保水性・通気性が良く肥料がないものがよい
- モウセンゴケの肥料は基本的に必要ない
- モウセンゴケの植え替えのタイミングは、1~2年に1回で冬の休眠期に行う
- モウセンゴケの増やし方は種まきや株分け、ムカゴで増やせる
- モウセンゴケは病気にはほとんどかからないが、害虫には注意する必要がある
- おすすめのモウセンゴケは、アデラエやハミルトニーなどがある

