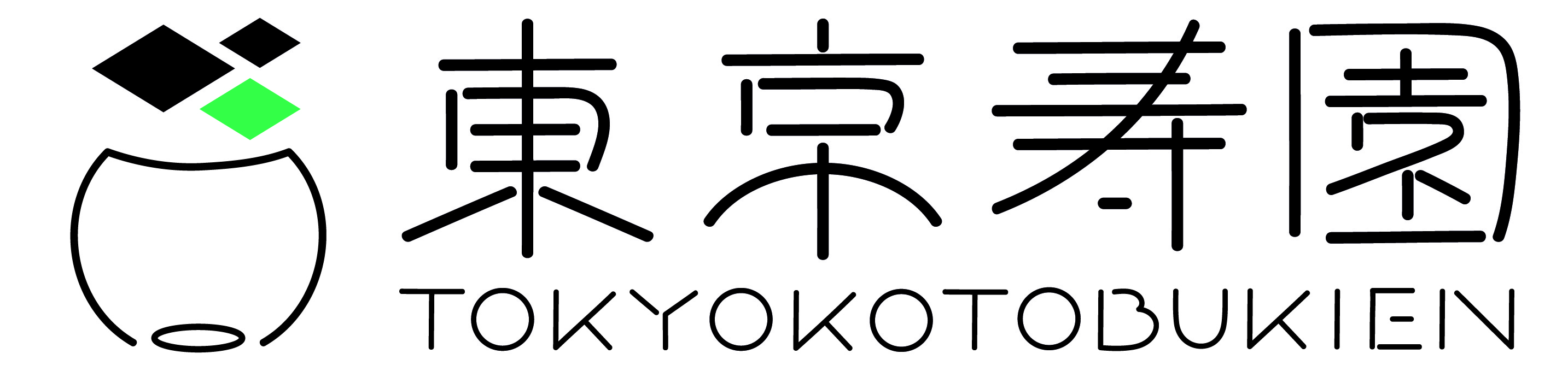目次
甘い蜜を出してハエなどを誘い込むハエトリソウ(ハエトリグサ)。誘い込んだ虫を葉を閉じてつかまえるハエトリソウは食虫植物を代表する植物です。そんなハエトリソウですが、実は慎ましやかできれいな花を咲かせることでも知られています。
この記事では、
- ハエトリソウ(ハエトリグサ)とは
- ハエトリソウの花の特徴
- 食虫植物ハエトリソウの花言葉
- ハエトリソウが花を咲かせるときの対処法と花の切り方
- ハエトリソウの上手な育て方
- ハエトリソウが食べる虫とは
ハエトリソウ(ハエトリグサ)とはどんな植物
ここでは、ハエトリソウ(ハエトリグサ)という植物について解説します。食虫植物として知られるハエトリソウの最大の魅力はその捕虫葉ですが、どのようにして虫をつかまえるのでしょうか。また、おそろしい別名をもつハエトリソウにはどんな種類があるのでしょうか。捕虫葉を持つ食虫植物
ハエトリソウは北アメリカ(東部沿岸の一部地域)の湿地帯に自生するモウセンゴケ科の食虫植物です。捕虫葉と呼ばれる葉っぱは独特の形をしており、2枚の捕虫葉を閉じてハエなどの虫を捕まえます。葉っぱにはとげがあり、立派なまつげを生やしたまぶたのような独特の形をしています。湿地帯に自生して多湿を好む性質から、ハエトリソウはテラリウムでの栽培も向いています。独特の姿かたちをしていますからテラリウムで飾るととてもおしゃれです。また、ハエトリソウは多年草で決まった寿命はありませんから、寿命ですぐに枯れるということはなく長く楽しむことができる植物です。捕虫葉の内側に2回触れると葉が閉じる
ハエトリソウの捕虫葉の内側には、感覚毛というトゲが生えています。この感覚毛に2回続けて触れると葉が閉じる仕組みです。葉が閉じて虫を捕まえると、消化液を出して消化し栄養に変えてしまいます。消化が終わるまで長い時間がかかりますが、その間、捕虫葉は閉じたままで開きません。 なお、水やりの時に捕虫葉に水をかけると捕虫葉が閉じてしまいます。捕虫葉を閉じることによって無駄にエネルギーを消費してしまうめ、水やりのときには捕虫葉に水をかけないように注意する必要があります。別名「ハエジゴク」
ハエトリソウの別名は「ハエジゴク」です。ハエにしてみれば、甘い蜜の香りに誘われて近寄ったらいきなり植物に捕食されてしまうわけです。ハエにとっては、まさに地獄と言えるでしょう。ハエトリソウは英語では「Vensu Flytrap」と呼び「女神のハエ取り罠」という意味になります。ハエを捕まえることには違いはありませんが、日本語では「地獄」、英語では「女神」と表現に違いがあって面白いですね。エレクタ系とロゼット系にわかれる
ハエトリソウは手に入れやすい手頃な価格帯のものが多いですが、園芸用に品種改良されたものを含めると100種類ほどの品種があります。ハエトリ草の種類は大きく、エレクタ系とロゼット系に分かれます。エレクタ系は捕虫葉を上に伸ばすのに対して、ロゼット系は捕虫葉を這うように広げるといった特徴があります。ハエトリソウは人気の食虫植物ですから、楽天などのネット通販でも多くのショップで取り扱いがあり、豊富な品揃えの中から手頃な価格で注文することができます。楽天などのほとんどのショップではハエトリソウの写真も掲載されていますから、写真を見て注文できて安心です。ハエトリソウはどんな花を咲かせるの?
ここでは、ハエトリソウの花について解説します。ハエトリソウの花を見たことはあるでしょうか。独特なかたちをした捕虫葉を伸ばす姿は有名ですが、ハエトリソウの花を見る機会は少ないものです。ハエトリソウは一体どんな花を咲かせるのでしょうか。個性的な見た目に反し可憐な白色の花を咲かせる
ハエトリソウの花を見る機会は少ないため、花は咲かないと考えている方も多いかもしれません。しかし、真っ赤な花を咲かせそうな個性的な見た目をしているハエトリソウは、実は開花の時期を迎えると可憐な白色の花を咲かせます。花茎を長く伸ばして、花茎の先端に白色の可憐な花を数輪咲かせます。もし花が咲かないなら、まだ開花の時期になっていないだけかもしれません。初夏の季節(5月~7月)が開花の時期
ハエトリソウが花を咲かせるのは、初夏の季節です。5月から7月の時期にかけて、涼しげな白色の花を咲かせます。花が終わると実をつけることがあります。受粉しないと実をつけませんから、種を採取したい場合には人工授粉などで受粉させます。植物を増やすことも植物を育てる楽しみのひとつですが、ハエトリソウは種まき以外にも株分けや葉挿しでも増やすことができます。ハエトリソウの花言葉
ここでは、ハエトリソウの花言葉について解説します。食虫植物ハエトリソウの花言葉は「嘘」と「魔性の愛」の2種類です。いずれもネガティブな花言葉ですから、花言葉を気にする方への贈り物には向いていません。しかし、子どもが興味を持ちやすい人気の食虫植物ですから、小学生などへの贈り物として適しています。また、ハエトリソウはアクアリウムなどで飾るとおしゃれですから、アクアリウムや食虫植物に興味のある方へプレゼントしてみるのもいいでしょう。「嘘」
ハエトリソウには「嘘」という花言葉があります。ハエなどの虫をだまして捕虫葉で捕まえる性質に由来します。人がつく嘘には相手を思いやっての嘘や可愛らしい嘘もありますが、ハエトリソウはウソをついて食べてしまうわけですからとても凶悪な嘘ですね。「魔性の愛」
甘い蜜を出して虫を誘い込むハエトリソウには「魔性の愛」という花言葉があります。虫を惑わせて捕食するハエトリソウにはぴったりの花言葉です。とはいえ、ただの魔性ではなく「魔性の愛」ですから、ハエトリソウは歪んだ愛情を抱きながらハエなどを捕まえて食べてしまうのでしょうか。ハエトリソウの花が咲いたらどうすればいい?
ここでは、ハエトリソウが花を咲かせるときの対処法について解説します。ハエトリソウの花を咲かせるべきか迷っている方もいらっしゃることでしょう。実は、花を咲かせるかどうかは、捕虫葉を元気に育てたい場合、花を楽しみたい場合、種を採取したい場合など目的によって対処法が変わってきます。花が咲くとエネルギーを使う
ハエトリソウの花が咲くときには花茎を長く上に伸ばして先端に数輪の花を咲かせますが、花を咲かせるためにはとても大きなエネルギーを使う、ということは知っておくとよいでしょう。花にエネルギーを使った分だけ、他の部分にエネルギーが回らなくなります。捕虫葉を元気に育てたい場合はカットする
食虫植物ハエトリソウの最大の魅力は、独特の見た目をした「捕虫葉」ではないでしょうか。捕虫葉を元気に育てたい場合には、花を咲かせるために多くの栄養をとられることは望ましくありません。花芽が出てきたらなるべく早く花芽をカットしましょう。花を咲かせることによってハエトリソウ全体が弱ってしまうこともあります。花を楽しみたい場合は残しておく
ハエトリソウの花を咲かせてみたい方は、花芽をカットせずに残しておきましょう。花を咲かせるために多くの栄養が必要になることは事実ですが、それによって捕虫葉がすぐに枯れてしまうわけではありません。とはいえ、枯れる可能性はゼロではありませんから、枯れる場合に備えて事前に株分けしておくと安心です。株分けを行う場合には、12月から2月の時期にそれぞれ3つほどの捕虫葉がつくように株を分けてから植え付けます。種を採取したい場合も花を咲かせる
ハエトリソウは5月から7月に花を咲かせた後、結実して種を採取することができます。種を採取したい場合には花を咲かせて結実させる必要がありますから、花芽をカットせずに残しておきましょう。受粉しないと種を採取できないため、花が咲いたら人工授粉などによって受粉させます。なお、ハエトリソウは種まき以外にも株分けや葉挿しでも増やすことができます。ハエトリソウの花の切り方
ここでは、ハエトリソウの花の切り方について解説します。捕虫葉を元気に育てたい場合は花を切る必要があります。しかし、花を切ると言っても、どこの箇所をどのように切れば良いのか悩みますよね。花に栄養を取られないようにすることと、切るときにハエトリソウを痛めないようにすることが花の切り方のポイントです。花芽を清潔なハサミで切る
ハエトリソウの花芽が出てきたら、栄養をとられないようなるべく早めにカットすることが基本です。カットするときには切り口から雑菌が入るのを防ぐために、清潔なハサミを使って切りましょう。切り口の断面を潰さないように、切れ味の良いハサミを使うこともおすすめです。花茎には栄養があるため残しておく
ハエトリソウの花茎には栄養が蓄えられています。花茎をカットしてしまうと栄養が捨ててしまうことになるため、花茎はなるべく残しておきましょう。ハエトリ草の花芽が出てきたら、なるべく早めに花芽をカットすることがおすすめです。ハエトリソウの基本の育て方
ここでは、ハエトリソウの基本の育て方について解説します。植物の育て方の基本となる置き場所や用土、水やりだけではなく、湿地帯に自生するハエトリソウですから湿度の管理にも気を配る必要があります。自生する環境に栽培環境を近づけてあげることが育て方のポイントです。日当たりの良い場所で管理
湿地帯に自生するハエトリソウですが日光を好む植物ですから、屋外の日当たりの良い場所で管理することが基本です。ただし、夏は日差しが強く葉焼けを起こしてしまうことがありますから、夏は直射日光に長時間晒さないことが大切です。ハエトリソウは屋内で育てることもできます。日光を好むハエトリソウを屋内で育てる場合には、日光のよく当たる窓辺がおすすめです。乾燥に弱いため腰水で湿度を管理する
湿地帯に自生するハエトリソウは、乾燥に弱い植物です。乾燥を防ぐためには、受け皿に2cmほど水を入れて腰水で湿度を管理します。腰水を行うことによって、鉢底から水を吸い上げて用土を湿った状態に保ちます。受け皿の水は2〜3日に一回は入れ替えるようにしましょう。保水性のある用土で育てる
湿度の高い環境を好むハエトリソウには、保水性のある用土が適しています。市販の培養土はハエトリソウにはあまり適していませんから、自分で用土を配合する必要があります。用土の配合は、鹿沼土、赤玉土小粒、ピートモスを同じ割合で配合するとよいでしょう。自分で用土を配合しなくても済む方法として、用土に水苔を使う方法もおすすめです。なお、ハエトリソウの用土は常に湿った状態に保たれているため、腐りやすくなっています。定期的に植え替えを行なって、用土を入れ替えることとよいでしょう。水苔を使って栽培する場合には、12月から2月の時期に毎年植え替えをする必要があります。土の表面が乾いたら水やり
湿気のある環境を好むハエトリソウにとって「水切れ」は大敵です。ハエトリソウの水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えることが基本です。冬の時期は土の表面が乾くまで時間がかかりますから、表面が乾かないうちに水やりをしないよう注意しましょう。水の与えすぎは根腐れの原因となります。また、捕虫葉に直接水が当たらないように水やりすることがコツです。捕虫葉に水がかかると捕虫葉が閉じて、成長に使うべきエネルギーを無駄に消費してしまうかもしれません。冬は休眠期に入る
ハエトリソウは1年草ではなく多年草ですから、はっきりとした寿命はありません。冬越しが必要になりますが、ハエトリソウは冬には休眠期に入ります。屋外で栽培する場合には、気温が0℃を下回らなければ屋外でそのまま管理して構いません。気温が0℃を下回る場合には室内に取り込んで冬越しすると良いでしょう。冬の時期に室内で管理する場合には、休眠期に暖かい場所で管理すると生育に悪影響があるため暖かすぎる部屋は避けることがポイントです。ハエトリソウはどんな虫を食べるの?
ここでは、ハエトリソウが食べる虫の種類について解説します。ハエトリソウを育てる理由のひとつは、捕虫葉を閉じて虫を食べる姿を観察することではないでしょうか。実はハエトリソウは虫以外のものも食べますから、虫が苦手な方でもハエトリソウが捕食する姿を観察することができます。主にハエを食べる
ハエトリソウの名前の通り、主にハエを食べます。ただし、害虫駆除のために大量のハエを捕まえることは期待できません。捕虫葉を閉じてハエを捕まえると、しばらくの間捕虫葉は閉じたままですから次々とハエを捕まえられないのです。なお、ハエトリソウは植物ですから、捕食した虫以外にも根っこなどから栄養をとることができます。室内で栽培している場合には虫を捕食する機会は少ないですが、栄養面ではわざわざハエなどの虫を与える必要はありません。虫以外にもタンパク質があるものを食べる
ハエトリソウはハエ以外にも、いろいろな生き物を食べます。蚊など小さなものから、蜂やバッタなど大きなものまで捕虫葉でつかまえてなんでも食べてしまいます。ハエトリソウが消化して栄養にしているのはタンパク質ですから、虫以外にもタンパク質を含む食材であれば代用ができます。虫は苦手だけれどハエトリクサに捕食させてみたいという方は、ハエなどの虫の代わりにタンパク質を含む食材を与えてみてはいかがでしょうか。チーズやゆで卵など身近な食材でもハエトリソウは捕虫葉でつかまえて栄養に変えてしまいます。食べられた虫は1週間かけて消化される
捕虫葉でつかまえられた虫は1週間ほどかけて消化されます。捕虫葉の中で虫が暴れてもよく強く締めつけて、消化液を出して消化します。消化が終わるまでの1週間ほど捕虫葉は閉じたままです。【まとめ】ハエトリソウのお花ってどんなの?特徴から扱い方まで徹底解説!
ここまで、ハエトリソウが花を咲かせるときの対処法から、花の特徴、花言葉、育て方の基本など詳しく解説してきましたがいかがだったでしょうか。 この記事のポイントは、- ハエトリソウ(ハエトリグサ)は北アメリカ(東部沿岸の一部地域)の湿地帯に自生するモウセンゴケ科の食虫植物。捕虫葉をもち内側に2回触れると葉が閉じ「ハエジゴク」の別名を持つ。種類は大きくエレクタ系とロゼット系に分かれる
- ハエトリソウは初夏(5月〜7月)の季節に可憐な白い花を咲かせる
- 食虫植物ハエトリソウの花言葉は「嘘」と「魔性の愛」の2つ
- ハエトリソウが花を咲かせるときの対処法は、捕虫葉を元気に育てるため花芽をカットすることが基本。花を楽しみたい場合や種を採取したい場合には花を残しておく
- 花の切り方は、花芽だけを清潔なハサミでカットして花茎は残しておく
- 湿地帯で自生するハエトリソウを上手に育てるためには、日当たりの良い場所で管理するとともに、腰水で湿度を管理する、保水性のある用土で育てるなどが育て方のポイント
- ハエトリソウは主にハエを食べるが、虫以外でもたんぱく質があるものを食べる。食べられた虫は1週間かけて消化される